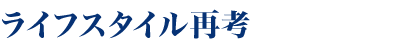
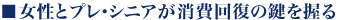

2012年10月9日国際通貨基金(IMF)・世界銀行の年次総会が東京と仙台市で開かれ(日本での開催は昭和39年以来48年ぶり2回目)、IMF専務理事は「女性が労働力として参画していかない限り、日本がうまくやっていくことは難しい」とし女性の労働参加の重要性を訴えた。日本女性の就業率
を20年で先進国7ヵ国並みにすれば、ひとり当たりの国内総生産は5%上がると指摘している。
日本の女性労働者の年齢階層別の労働力率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は近年"M字型曲線"を描かなくなりつつある(図表1)。これは主に25歳~39歳の働く女性が増えたことに起因し主体的に晩婚・晩産を選ぶ女性が増えた結果と言えよう。
■図表1 女性の就業率の変化
一方で欧米諸国の女性の労働力率(就業率)は逆U字カーブを描く。日本よりも地域の子育て環境が充実しているなど、基本的な雇用・社会システムが異なる。日本的経営の三種の神器と言われる"終身雇用"、"企業別労働組合"、"年功序列"の慣習が色濃く残る限り、日本女性の労働力に関して本当の意味での定着化は難しいと言わざるを得ない。だが、働く女性が増えつつある今、日本の個人消費という側面で"女性の力"はどう寄与していくのだろうか。また、高齢化率が23.3%に上昇した日本において、底堅い内需を支えているのは団塊世代に代表される60代及び50代を含む"プレ・シニア"である。現役世代が減る中でこの2つの観点を中心に今後の消費を考えていく。
◆2012年度ライフスタイル調査概要
ここからは弊社が2000年から毎年秋に継続して実施しているライフスタイル調査の結果を基に生活者動向を見ていく。
■調査期間
2012年9月24日〜10月15日
■調査対象者
全国18歳以上男女
■調査方法
弊社モニターによるインターネット調査
■分析サンプル数
※分析にあたっては性年代などによる人口構成比に合わせたウェイト付けを行っている。
2012年10月時点の「日本社会の展望と自分の生活」について、「自分の生活も日本社会も悪い方向に向かっていく」という評価が47.7%と最も高い。自分の生活にも日本社会にも展望を持てないという認識が生活者ベースにあり、女性(44.8%)よりも男性(50.5%)の方が高い。特に男性30代〜60で5割〜6割弱と高く(図表2)、反対に20代と女性30代の比較的若い年代で「自分の生活は良い方向に向かっていく」とする意識が相対的に高い。
■図表2 日本社会の展望と自分の生活
次に「幸福度」と「生活水準」(図表3)を見ると幸福度は女性の方が男性よりも総じて高く、自身の生活を肯定的に捉えている様子が伺える。生活水準においても女性20代を除く、30代〜60代の女性の「下・中の下」とする比率が男性よりも低く、男性の方が悲観的と言えよう。女性20代は、有職/無職、フルタイム/パートアルバイトなどの就業形態によって生活水準の評価差が顕著であるが幸福度は同じ就業形態の男性よりも高い。たとえ生活水準の差こそあれど"今"を肯定的に捉え将来の見通しに対しても良い方向に向かっていくとするこの女性の気組みこそが日本の消費回復を牽引していくのではないかと考えられる。
■図表3 幸福度と生活水準
この背景には、どのような価値観が潜んでいるのだろうか。本章では仕事・結婚などの価値観や考え方に注目した。まず「①結婚したい相手がいなければ結婚しなくても良い」という意識は女性の方が圧倒的に高い(図表4)。この意識は女性50−60代においても同じで、女性20代の独身女性(娘)の結婚意識と同調している。晩婚化が進み独身女性が増える中で母と娘が2人で一緒に消費を行う"母娘消費"が注目されているが、その根底には結婚がすべてではないという価値観の共有があると考えられる。そして「②結婚しても独身時代とは変わらずステキだと思われたい」という意識も同調しており、男性よりも欲望を明確化するポテンシャルが高い。もはや女性にとって結婚は"しなければならないひとつの目標"ではない。この考え方に反論する人も減ってきている。時間の経過と共に結婚の意味は変質していき"幸せな結婚ならしたい"という意識が主流になりつつある。さらに「③結婚後も自分の時間や友人との時間や友人との時間は一切減らしたくない」という意識が付帯し「④自分ひとりでも生きていけるぐらいの生活能力は必要だ」という意識とリンクしていく。
■図表4 仕事・結婚観「5.非常に+4.まああてはまる」
これらの女性の価値観は "結婚・出産・子育てを期に家を買う"という低頻度高単価商材の購入機会を遅らせることにつながるものであるが、人生で最も高額な買い物である住宅及び住宅設備に対するこだわりは男性と同水準、またはそれ以上である(図表5)。なお、年代別では50−60代の住宅に対するこだわりが最も強い。
普段の買い物行動については「③買い物に出かけるのが好きである」や「④ついつい衝動買いしてしまうことがある」という潜在的な購買意欲に関する意識も女性の方が高く、女性が消費を牽引していく可能性が高いと見られる。
■図表5 住まい意識と買物意識「5.非常に+4.まああてはまる」

具体的にどのような消費が見込まれるのだろうか。「値段が高くても購入したもの」という質問の回答結果を見ていく(図表6)。第1位は「①ファッション」(全体25.3%)である。次に「②旅行・レジャ―」(全体21.0%)、「③食品」(全体17.3%)が続く。「①ファッション」では女性の購入意欲が男性よりも総じて高い。「②旅行・レジャー」は主に女性50代、60代が高い。このプレ・シニア層は"登山ブーム"を巻き起こした層であり、昨年後半から"パック旅行"の利用者数も増加傾向にあるなど、堅調な消費の一角を担っている。また女性30代は同年代の男性に比べて「②旅行・レジャー」への意欲が高いなど、今年話題となった東京スカイツリー・ソラマチ観光、渋谷ヒカリエといった新しい観光消費は今後もプレ・シニア層及び女性30代が牽引していくものと考えられる。「③食品」では女性30代〜60代での性差が大きい。今年のヒット商品であった塩麹など、女性向け商品のヒットの背景にはこのような女性の購入意欲があったと見られる。
一方で男性は「④AV機器」(全体16.9%)や「⑤情報通信機器」(全体13.1%)において女性よりも総じて高い。男性50代、60代の購入意欲も男性30代、40代と同等水準であり、今の男性50−60代は気持ちも若くパソコンやスマートフォン、タブレット端末など30代、40代と同じものを使いたいという意識が強いと考えられる。家電量販店のパソコンサポートクリニックは新設オープン後1時間で満員大盛況であり本格的にシニア需要が立ち上がったと言われている。他方で若い年代における情報生活・インターネットに関する行動意識は男性と女性で大きく異なる。女性20代は「人間関係を広げる重要なコミュニケーションツール」(32.8%)という意識が強く「実際に会う機会を持つようにしている」(20.4%)など、インターネット上の接点・情報こそ実世界で活かそうという意識が強い。それに対し男性20代は「お金がかからないのでネットで遊ぶことが多い」(35.1%)など保守的である。今年爆発的にユーザが増えた「LINE」(スマホアプリ)の主なユーザは若年層の女性であり「スタンプ」の売上は今や月3億円以上とも言われている。日本経済の自律回復、そして拡大の鍵を握るのは女性とプレ・シニアに掛かっていると考える。 (田中 庸介)
■図表6 値段が高くても購入したいもの:上位①~⑩
※本提言「ライフスタイル再考」は、「営業力開発」誌 2012年・No216号(編集発行:日本マーケティング研究所 執筆担当:JMRサイエンス)へ掲載されています。尚、誌面では以下の様な構成にて続きます。
「ライフスタイル再考」

Ⅰ.女性とプレ・シニアが消費回復の鍵を握る
Ⅱ. 「家中」生活を充実させる
Ⅲ. プレ・シニアの情報探索と買物行動
Ⅳ. マーケティング戦略のリアリティ
|